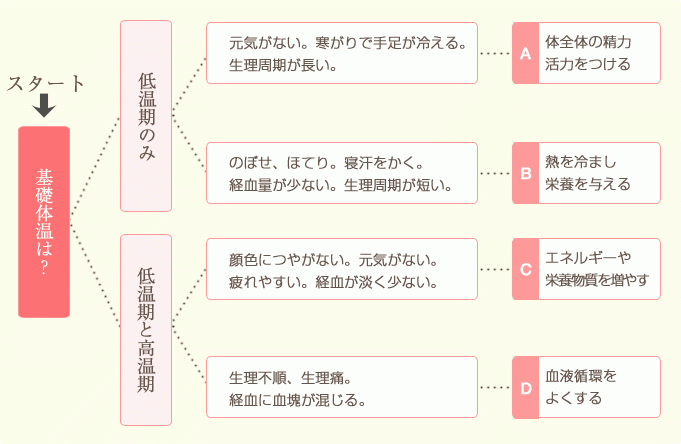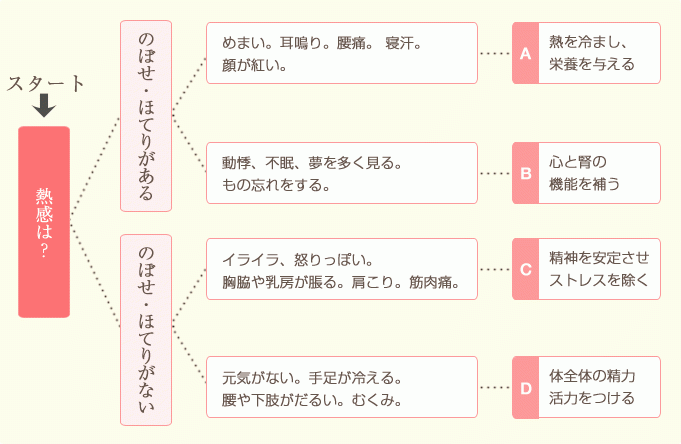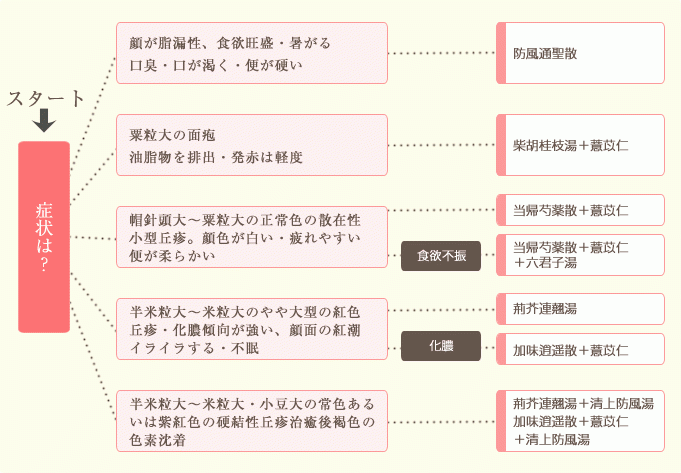漢方薬で対応できる症状の一例をご紹介
SYMPTOMS
不妊や生理不順、耳鳴りやアトピーなど様々な症状を改善できるのが漢方薬です。お客様の症状とともに体質にも合わせた漢方薬を提案いたしますのでお気軽にご相談ください。また更年期障害や若年層のニキビ、不眠といった医学的な処置では原因や治療法を特定することが難しい症状に対しても改善効果が期待できます。多くの方の相談に対応した実績のある薬剤師がご相談に対応いたします。
卵管が詰まっている場合や排卵が上手くいかない場合には気の流れや血の流れ、痰湿などが関係している場合が多く、改善する処方がございます。排卵がスムーズに行われない場合は、気滞や痰湿お阻などが考えられます。体質や生理の状態を問診し、問題があるところを改善する処方が必要となります。これらの処方がその方にあっていれば通常1ヶ月の服用で今まであった症状は改善されてきますので、効いているということが実感できます。
訴える症状としては、頭痛やめまい、耳鳴り、憂鬱、のぼせ、冷え、動悸、倦怠感、脱力感、不安感、血圧の異常、記憶力の低下、集中力の低下、発汗、しびれ、性欲減退、あるいは性欲の亢進、食欲不振、頻尿、下痢あるいは便秘、肩こりなど実に多彩です。漢方薬でほとんどの場合、早い時期に症状が良くなっていきますので、ご相談ください。以下のように出てくる症状によってタイプ分けして治療します。
アトピー
SYMPTOM03
アトピー性皮膚炎でお困りのお客様からのご相談は非常に多く、できるだけ自然からできた漢方薬で体質から改善したいと言われます。薬心堂漢方薬局では、患部の赤み、皮膚の乾燥、かゆみの程度や、どんなときに悪化するのか、かくと浸出液や血が出るのかどうか、また、全身症状としては、胃腸の症状や精神状態などを詳しくお聞きすることから、どんな漢方的な原因でアトピーが発生しているのかを特定した上で、そのお客様に合った漢方処方を決定しております。複数の漢方薬の処方が必要なことも多いです。
年代別のアトピー性皮膚炎の特徴
乳幼児の場合
呼吸器系(五臓で言う「肺」にあたります。ここで言う肺は皮膚を含みます。)と胃腸などの消化器系(五臓で言う「脾」にあたります。)の二系統が弱いことが多く、呼吸器系(鼻アレルギーや気管支喘息など)のトラブルをともなっているお子様です。下痢や食欲がないなどの消化器系の症状を伴う場合もございます。漢方薬は、呼吸器系と消化器系を強くするような漢方処方を中心に使うと良くなることが多いです。
成人のアトピーの場合
成人型のアトピーは、幼少のころは皮膚の症状はなかったのに、20歳代の前後などになって、アレルギー性の慢性湿疹があらわれるケースです。就職などによる精神的なストレスや食事の偏り、飲酒や喫煙、睡眠不足、疲労の蓄積、部屋が不衛生などにより発生してきます。中国医学的には「腎虚」の症状が見られることが多く、呼吸器と腎を強くする漢方処方を中心に使うと改善することが多いです(ここで言う腎とは腎臓のことではございません。)。
症状に合った漢方処方をお続けいただくことによって、炎症が起きる原因から改善するのが漢方のやり方です。赤味や乾燥肌なども、服用開始から割合と早い時期から改善される方が多くいらっしゃいますので、ぜひお試しいただきたいと思います。
ニキビ
SYMPTOM04
ニキビのご相談も薬心堂漢方薬局では、1年を通じて多くお受けしており、漢方薬が奏効する場合がほとんどですので、ぜひお試しください。今までに様々な治療方法を試したのに良くならなかった方や、一度よくなっても再発を繰り返している方にもお試しいただきたいと思います。
年代によるニキビの原因
10代のニキビ
ホルモンバランスの乱れや、皮脂腺の発達により脂が過剰に分泌してきます。脂の排泄がうまくいかないと10代のニキビなることがございます。年齢を重ねるとだいたいできなくなりますが、上手にお手入れをしておかなければ跡が残ってしまうとこがございますので注意が必要です。刺激にならないような洗顔や、ニキビをつぶさないということが大切です。また、漢方薬による体質に合わせた治療をお試しいただきたいと思います。
20代以降、30代のニキビ
この年代はストレスが原因でニキビとなることが多いです。仕事や生活環境が変わったことがストレスになってニキビが出てくる方が多く、寝不足が原因になっている方もいます。漢方薬が効果を発揮することがほとんどですのでぜひご相談ください。
生理不順
SYMPTOM05
周期が延長する、短縮する、不定期の場合があり随伴症状によって判断いたします。器質的な異常や全身性の病気がある場合には、原因となる病気の治療が必要ですので、専門病院での診察が必要です。具体的な漢方薬の処方名は書いておりません。同じような効果を持つ処方が多数あり、その方の症状で微妙に合うものが違うからです。数種類の処方を同時に服用する必要があることも多々ございます。
自律神経失調症
SYMPTOM06
症状や体質に合った漢方薬により症状が軽くなる方が多い病気のひとつです。 また、病院の薬を服用されている方で漢方薬を併用できます。漢方薬は症状や体質に合っていれば、比較的副作用の心配が少ない医薬品です。 自律神経は内臓や血管に広く分布しており、心臓の動きや、血管の収縮・拡張、呼吸、食べ物の消化、体温調節、気管支の収縮・拡張、汗腺、目の涙腺、口の唾液腺、膀胱などをコントロールしている神経です。 自律神経の中枢は脳の視床下部や辺縁系と呼ばれる場所にございます。
自律神経失調症の原因
自律神経失調は、この中枢に働きかけることによって起こります。原因としては3つあります。
1. 体の内部で発生する変化、女性の更年期のホルモン減少などです。
2. 体の外の刺激、急激な暑さや寒さ、激しい運動などです。
3. 最も多い原因が、感情の刺激で不安、心配、恐怖、怒りなどです。
自律神経失調症の症状の例
のど:のどに異物感がある、のどが詰まる。
心臓:突然動悸がする、不整脈。
身体:疲れやすい、めまいがする、寝つきが悪い、肩こりがある。
手足:冷える、ほてる、しびれる。
胃腸:食欲不振、下痢、便秘、ガスがたまりやすい。
目・耳・口・頭:目の疲れ、耳鳴り、耳の詰まり感、頭痛、口が乾く、頭が重い。
(これらの症状が一定していないのが特徴です。)
自律神経失調症の特徴
いろんな自覚症状があるのに、検査をしても異常がなく、気のせいと言われることもございます。自律神経失調症が原因で神経症やうつ病になることもございます。どこまでが、自律神経失調症なのか明確に分けることは難しいのが実情です。
耳鳴
SYMPTOM07
一言に耳鳴りと言いましても、様々な訴えがございます。音の種類も、ジーン、キーン、ピーといったものから、蝉が鳴くような音、波のような音、鐘のような音、風のような音など様々です。病院では耳の検査をして異常がなければ、これといった治療法もないために、お悩みの方が多いのが実情です。
漢方では、以下のように分類して症状や状態に合った漢方薬で治療します。
1. 風邪をひいた後に発生した耳鳴り
2. 思うように日常生活が運ばなかった後で発生した耳鳴り
3. 強いストレスを受けた後で発生した耳鳴り
4. 疲れるとひどくなる耳鳴り
5. 飲食の乱れが続いた後で発生した耳鳴り
耳鳴り以外の症状をお聞きすることも、処方を決めるためには非常に大切ですので、様々な角度からご質問いたします。効果が出てくるまでの日数は、早い方では1ヶ月以内に耳鳴りが小さくなる方もいらっしゃいます。症状や漢方的な原因によっては長い期間の服用によって改善される方もいらっしゃいますので、他の症状に比べると根気が必要です。
不眠症
SYMPTOM08
漢方での不眠症に対する考え方
不眠は心だけが原因ではなく、漢方では全身の症状が関係していると考えています。
漢方では身体症状を治療し、心と身体の調和をはかることによって不眠を改善していきます。症状や体質に応じて適切な処方を決める必要がありますので、寝つきだけではなく普段の身体と精神状態を詳しくお伺いいたします。
漢方薬を特に試していただきたい方
抗不安薬を服用して寝ている方の中には、朝目覚めてもしばらくは頭がすっきりしない、一日中眠い、だるくて困る、身体に力が入らない感じがする、といった症状でお困りの方もいらっしゃいますが、漢方薬ではこのような症状で悩まされることはございません。また、抗不安薬を服用しても効果が出にくい方にも、お試しいただきたいと思います。
不眠の漢方薬の特徴
漢方薬は、不眠症を根本的に治療していきますので、不眠が改善してくれば量を減らしたり、最終的には服用しなくても眠れる身体を作っていきます。不眠以外の症状を良くお聞きして、症状と体質に合った漢方処方を見つけることが必要となりますので、不眠の症状も詳しくお伺いいたします。身体に合った漢方処方を服用すれば、不眠以外の症状も改善されてきますので、ぜひご相談ください。
蕁麻疹
SYMPTOM09
蕁麻疹とは、肥満細胞から放出されるヒスタミンにより起こる一過性の浮腫をいい、痒みをともなう赤い発疹が突然現れ、数時間で消滅する皮膚の病変です。発症時の皮膚は夏皮の血管が拡張するとともに、血液中の血しょう成分が皮下に滲み出た状態になり、皮膚の上から見れば赤い膨疹と見受けられます。主な隋伴症状としては痒み、局所の熱感、不快感、時に頭痛を覚えます。現在、蕁麻疹の70%は原因が特定できません。推定できる主な原因としては次のようなものがございます。
主な原因
1. 薬物
2. 食品(魚介類、卵、牛乳、大豆製品、蛋白質を含む物)
3. 浮遊物質(ほこり、花粉)
4. 接触(蜂、ダニ、化粧品)
5. 温度(寒い風、冷え、のぼせ)
6. ストレス(特に原因不明の場合)
7. 物理的刺激(掻き傷、日光、運動、入浴、肌の乾燥)
8. 細菌(2次感染)
治療
皮膚症状や隋伴症状をもとに治療を行います、いくつかの検査(IgE等)の組合せも重要です。原因がうまく特定できない場合、食事日記、行動パターンから蕁麻疹の発生パターンが判明できることがございます。治療薬として最もよく使われるのは、抗ヒスタミン剤です。特に急性の場合は、原因が特定できなくても、アレルギー反応は防ぐことができますので、かなり効果がございます。ただし、人によっては非常に眠くなりますので、生活に支障をきたす恐れもあり、注意が必要です。漢方薬なら安心して飲むことができ、薬効開始も早いです。外用も重要なポイントで、痒みが強い場合は、ステロイド剤と抗ヒスタミン剤、抗ヒスタミン剤以外の抗アレルギー剤を併用することもございます。
1. Ⅰ型アレルギー(即時型)による症状
一般的に赤く地図状に腫れる蕁麻疹です。
2. 掻いた痕が赤くなり、続いて白く退色して痒みがある
アトピー傾向があるとか、ストレスが強い人に出る局所血管の収縮する蕁麻疹で、抗アレルギー薬で充分な効果が得られず困ってこられる場合が多いです。
3. 海産物(海老、蟹、青魚等)で発生する蕁麻疹
あるいは、何度も再発する蕁麻疹です。
4. 蚊、ブヨ、シラミ、ダニ、南京虫等の虫刺され
蜂に刺されますと、2回目からはアナフィラキシーショックを引き起こすことがございますので、注意が必要です。
5. 日光蕁麻疹
特に春から夏にかけて日光に当たると、直後から2日目くらいに日光に当たった部分に紅斑、湿疹、水疱が発生してきます、皮膚に付いた化学物質、キノリン系抗菌薬、ピロキシカム等の薬品が下地にあり、日光に当たることにより発症することもございます。
風邪による蕁麻疹
中国医学では「風疹」と言います(風→風邪によって疹→発疹がでる)。西洋医学の「風疹」とは違う特徴としては、毎日起きていても、以下のように
1. 突然出る。バーっと出ても4時間ほどで治る。
2. 皮フ粘膜、上半身に出る。
3. 痒みがある。
これらは、風邪が原因です。
風邪には外風と内風とがございます
1. 外風
風邪によりますが殆んど風邪がキッチリ治らず、風邪症状はなくて風邪は治ったがスッキリしない時、風邪を除ききっていない、その外風が体表部の血行を乱し蕁麻疹が出ます。
2. 内風
もっぱら食物に関連します。生ゴミを出していると臭くなっていくように、生ゴミが悪臭を放つ、風のって漂ってくる、生ゴミより風を生じた食べて蕁麻疹、主にエビ、カニだが、消化しにくく、脾胃に負担がかかる、湿濁を生じ、加熱します。熱により、風を生じる、風を血流を乱し、蕁麻疹が出ます。
お通じ(便秘)
SYMPTOM10
便秘とは、毎日便通が無いことや毎日便通はあるが排便に時間がかかること、便の質が硬いことなどです。便が大腸内に長時間滞留すると、腸内細菌に良くない影響を与えます。便が悪玉菌のエサとなり悪玉菌が増殖し、発ガン物質や発ガン促進物質、アンモニア、硫化水素などの有害物質を発生させてしまいます。これら有害物質は、便の排泄ができないと、腸から体内に吸収されてしまい、血液に入り込んで全身に流れ様々な良くない症状を引き起こすと考えられています。
主な原因
熱結便秘
熱が大腸に結するとおこる便秘で、生来陽盛体質の方、熱性疾患の方、酒の飲み過ぎ、辛い物・脂っぽい物の過食、温熱性の生薬を過服などが原因です。
気滞便秘
気の運行が滞ると胃腸の動きが弱くなりおこる便秘で、憂鬱、怒り等ストレス(緊張や環境変化)、咳・喘息による大腸の気の停滞、運動不足、腹部の手術後などが原因です。
気虚便秘
主として肺気虚および脾気虚が原因となる便秘で、脾気の不足、肺気の不足、慢性疾患・手術・出産などによる脾気の消耗などが原因です。
陽虚便秘
陽虚は消化不良、軟便、下痢など便秘とは逆の症状を引き起こす事が多く、陽虚体質の方、老齢による機能減退、冷飲・冷食、長期にわたる寒涼性生薬の過服などが原因です。
血虚便秘
滋潤作用をもつ血が不足し、腸管内が乾燥しておこる便秘で、血虚体質の方、胃腸・痔・子宮の出血など出血疾患、月経期間中の一時的な血の不足、出産による出血などが原因です。
陰虚便秘
血虚便秘と同様、陰分が不足する胃腸の乾燥症状によりおこる便秘で、陰虚体質の方、熱性疾患の方、汗や下痢の症状、乾燥性の強い生薬の過服などが原因です。
薬心堂漢方薬局おすすめの改善方法
快便セット
無理やり出す「下剤」ではなく、腸にこびりついたドロドロ宿便をキレイにする「腸内浄化法」です。初めて飲んだ方の8割が「こんなに出るの?」と驚かれます。
乳酸菌FK-23菌含有食品
「悪玉菌」が多い状態を「善玉菌」の援軍を送り込むことで、優勢にしもうひとつの腸内にある「日和見菌」を「善玉菌」の味方にするよう働きかけます。「善玉菌」が多くなることで、整腸力が強まり便秘の解消につながります。
痔
SYMPTOM11
痔は肛門疾患に所属する、老若男女を問わず患う人の多い大衆病です。命に関わるような疾患ではございませんが、日常的に不快感や苦痛を伴うので、積極的に治療し、安定状態を維持したい疾患でもあります。漢方による痔治療の歴史は長く、その経験を活かして根治をはかります。
痔の分類
牡痔 | 外痔 |
|---|---|
牝痔 | 内痔 |
脈痔 | 化膿して、痛痒く出血する痔 |
血痔 | 出血する痔 |
気痔 | 怒ると発病する痔 |
酒痔 | 飲酒すると発病する痔 |
色痔 | 性生活の後に発病する痔 |
腸痔=人州出 | 脱肛 |
肛瘻 | 痔瘻 |
主な原因
飲食の失調
暴飲暴食、飲酒、辛い物、甘い物、油物、生物、冷食などの過食などが原因です。
大便の失調
便秘、下痢などの排便異常などが原因です。
運動の失調
坐ったままの生活、立ち仕事、荷物の運搬など偏った運動などが原因です。
妊娠・多産
出産経験の多いことなどが原因です。
慢性疾患
慢性消耗性疾患、肝臓・心臓の疾患、子宮筋腫などが原因です。
改善方法
出血の場合
地楡・槐角・槐花・荊芥穂・烏梅・生地黄・当帰などの涼血止血・養血和血の生薬で、出血を止めます。
疼痛の場合
川楝子・芍薬・木香・紅花・川芎・当帰・桃仁などの理気・活血の生薬で、局部の気血の流れを改善し、疼痛を止めます。
痒みの場合
防風・蒼朮・黄柏・茵蔯蒿・苦参などの去風・燥湿の生薬で、局部の湿邪を除去し、風邪を発散して痒みを止めます。
化膿の場合
黄芩・金銀花・黄連・薏苡仁・白芷などの清熱・燥湿の生薬で、局部の湿熱邪を除去させ、化膿状態を乾燥させます。
下痢の場合
木香・車前子・白朮・山薬・茯苓などの健脾・摻湿薬で、脾胃の湿邪を除去しながら、下痢を改善します。
便秘の場合
麻子仁・柏子仁・杏仁・大黄・番瀉葉などの潤腸・通便あるいは瀉下・通便薬で腸内の積滞を除去して、便秘を緩和します。
痛み
SYMPTOM12
痛む箇所・痛みによってお薬が異なります。部位や痛みの種類によって適切なお薬を飲むことで痛みを和らげたり、早く改善が見込まれたりします。
主な原因
頭痛 | 締め付けられるような痛み・吐き気を催す偏頭痛・気候/天候によって頭痛を予兆できる症状 |
|---|---|
肩・首の痛み | スマホ/パソコンによる肩こりや疲れからくる痛み・起床時高血圧によっておこる筋の痛みや腫れ |
腰痛 | ぎっくり腰・日頃の疲れからくる痛み |
手足の関節痛 | 捻挫・リュウマチ・腱鞘炎・運動によって起こる痛み |
腹痛・胃痛 | 胃炎・腸炎による痛み |
シーズンの症状
SYMPTOM13
梅雨:湿気が体の中に入り込み、気の流れが悪くなることが原因でだるくなったり関節の動きが悪くなったりなどの症状が出やすくなります。
夏:汗をかいて水分を取りすぎたり冷房の効いた部屋に長時間いたりすると気の流れが悪くなったり熱中症を引き起こしたりするなどの症状が出やすくなります。
その他
SYMPTOM14
・下痢 ・口内炎 ・目の疲れ など